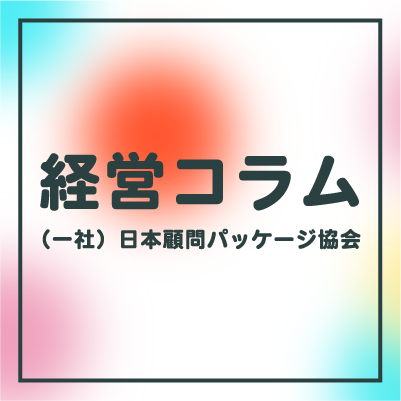みなさん、こんにちは。
契約の基礎の第2弾をお届けします。
トラブルの多くは「何を・どこまで・どういう質で」やるかの認識ズレが原因です。
だからこそ「契約給付の内容」を先に丁寧に決めておきましょう。
読み手(相手)にも伝わる、やさしい設計がカギです。
■ 何をやるの?(スコープの明確化)
・対象業務・成果物を列挙(含む/含まない)
・仕様・要件・前提条件
・第三者ツール・素材の扱い
→やること・やらないことを線引きしましょう。
■ どんな質で?(品質・基準)
・性能指標/納品基準/検収基準(合否の物差し)
・応答時間・稼働率・再実施条件
・適用ガイドライン・法令・業界標準
→「良い」の定義を数字や判定で示しましょう。
■ いつまでに?(スケジュール・マイルストーン)
・工程表(設計→実装→テスト→納品)
・中間成果物とレビュー日程
・遅延時の手当(報告・復旧計画)
→見通しと合意のポイントを地図化しましょう。
■ どうやって決めて進める?(体制・役割・承認)
・担当者・責任分担
・連絡手段・会議頻度・報告様式
・承認フロー(誰が・いつ・何を承認)
→意思決定の道筋を決めておきましょう。
■ 変わったら?(変更管理・追加費用)
・変更申請→影響分析→再見積→合意の手順
・増減の単価・計算式
→“後からの変更”のルールを先に置きましょう。
■ 材料と成果の扱いは?(知財・データ)
・著作権・利用許諾・二次利用の可否
・下書き・設計図・ソースの帰属
・個人情報・機密データの処理
→作るもの/使うものの権利と安全を明確に。
■ 受け取り方は?(検収・受領手続)
・納品形式(ファイル形式・媒体・提出先)
・検収期間・差戻し・再納品期限
・みなし検収(例:7日間異議なしで合格)
→受け渡しの“最後の一手”を詰めておきましょう。
■ 想定外に備える(除外・前提・依存関係)
・サービス外事項・環境要件(例:顧客の準備物)
・他社システム依存・外部要因のリスク
・試験データ・実環境の準備責任
→できないこと・頼るものを先に宣言しましょう。
契約書の作成のヒントにしていただければ幸いです。
第1弾の「終わらせ方」とセットで、安心して進められる契約に。
(田鍋/編集 中路)