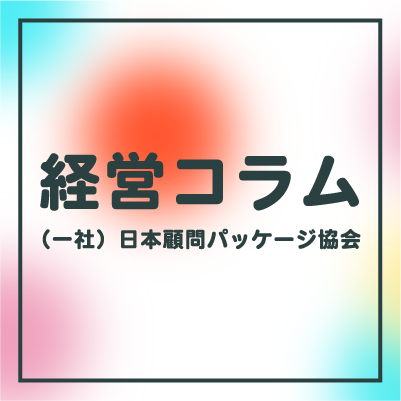みなさん、こんにちは。契約の基礎の第3弾をお届けします。
「納品されたけど思っていたのと違う」
「運送中に壊れた、誰の負担?」
――現場でよく起きる悩みはここに集約されます。
だからこそ【契約不適合責任】と【危険負担】を、先にやさしく設計しておくことがポイントです。
■ どこまでが“適合”なのか?(不適合の定義と範囲を確認しましょう)
・対象:数量・品質・性能・仕様・包装・表示・ライセンス状態
・基準:仕様書・見積・サンプル・図面・カタログ・検収基準
・除外:試作品の誤差許容、自然素材の個体差 等
→「何が適合か」を書面で示し、証拠(仕様書・見積)のひも付けが大切です。
■ 不適合があったらどうする?(買い手側の手当)
・追完:修補/交換/不足分の補充(期限・回数・費用負担)
・代金減額:算定式(例:価値差×%)
・損害賠償:範囲(通常損害/特別損害の要件)、上限額
・解除:重大不適合・追完不能・期限の利益喪失の扱い
→“優先順位”を決める(①追完→②減額→③解除 等)と揉めにくいでしょう。
■ どうやって見つけて、いつまでに言う?(検査・通知)
・検査:方法(目視/機能試験)、場所、立会い、記録様式
・通知:期限(例:受領後◯日、隠れた不具合は判明後◯日)
・保全:使用停止・隔離・写真/ログ保存・第三者検査の可否
→「検査プロセス」と「通知期限」を明文化し、証跡を残す運用が重要です。
■ 誰がいつまで責任を負うか?(存続期間・保証)
・保証期間:開始点(引渡/検収合格から)、期間、除外事由
・再実施:再納品後の保証リセットの有無
・消耗品/ソフト:アップデート・脆弱性対応の範囲
→期間・開始点・リセット有無の3点セットで抜け漏れ防止となります。]
■ 想定外の破損は誰の負担?(危険負担の起点)
・リスク移転時点:引渡し/検収合格/運送人渡し 等を特定
・不可抗力:天災・停電・ストの扱い、誰が費用・再製作を負担するか
→「いつ」「どこで」危険が移るかをきちんと条文化しておきましょう。
■ 万一に備える設計(上限・証拠・費用)
・賠償上限:直近支払額×◯倍/上限◯万円、除外(故意・重過失)
・立証:ログ・検査成績書・第三者鑑定、費用負担と回収方法
・費用:引取り・再納品・現地修補・停滞コストの負担区分
→“お金の出口”を数式と役割で決め、後出しを防ぐことを意識しましょう。
契約書づくりのヒントになれば幸いです。
第1弾「終わらせ方」、第2弾「契約給付の内容」とセットで、
“合意→実行→検収→万一”までの道筋を一本化しましょう。
(田鍋/編集 中路)